
趣 意
医療の担い手として、長年、患者や家族のケアに携わってきたことで、生命の誕生から今に至る連綿とつながった、「いのちの最前列で今を生きる私たち」がいかに奇跡であるかを知りました。
また、いきいきと生きた「いのち」が、死によって次の世代に受け継がれれば、それは温かい灯となって次の世代の足元を照らすということも確信しました。
これを「いのちのバトンリレー」とするならば、この「いのちのバトン」は自殺、虐待、無縁社会、戦争といった悲しい出来事をなくしてくれるバトンとなると考えます。
母親は子を産んだらすぐ子育てを始めるのが動物界の自然であり、また、苦しい介護をしたからこそ家族の死や介護の意味を受け入れ、乗り越え、その後の人生が輝くことも、家族を見送った多くの方から教わりました。
ところが、暮らしの中に当たり前にあった「バトンリレー」が難しい社会になってきています。
このバトンリレーは、今や、病を診る仕組みであるはずの医療に任せるざるを得ない状況となり、これにより起こっている問題は、人の在り様のみならず、社会の仕組みをも揺るがしかねない大きな危機的要素を孕んでいます。
医療技術の進歩や保険制度の充実により、わが国はまれにみる長寿国になりました。
しかし、現実には有病率が下がったわけではなく、老いをも病として医療が診るようになってきた結果、「病気」を持ちながら長生きしているのが現状です。
誰もが平等に医療が受けられることは、日本が世界に誇れる素晴らしい仕組みかもしれません。
ところがその仕組みがもたらしたのは、医療への誘導と結果としての依存でした。
生活から発生してくる病を医療だけで解決しようとすることで、そのひずみが様々な問題を引き起こしています。
これらの問題は、医療行政や医療を提供する側の問題と捉えられがちで、意思決定支援や受け手とのよりよい関係構築に解決策を見出そうとしているのが医療側の思いです。
しかし、その受け手である医療を利用する側にも、主体的に心や身体に向き合おうとする姿勢が必要なのではないでしょうか。
残念ながら、既存の教育はこの問題やひずみの根本に着目しておらず、また医療が人々の生活の質を高められるようなあり方に方向転換することも不可能でしょう。現に、人が「いきもの感覚」を取り戻し、自然治癒力への基本的な信頼を育むことができるような情報提供や体験の場は、医療とは隔たりのあるものとして同一線上で語られないばかりか、根拠のないものとして国を挙げて排斥してきた歴史さえあります。
生態系の頂点に立つ「人」が自然の仕組みを知ることで、人と自然というあらゆるいのちとのパートナーシップの再構築に寄与でき、さらに「いのちのつながり」の中で育ちあえれば、必ずや社会の再生につながると確信しています。
そこで、このたび、「自然の一部である人」を知り、「自然そのものである人」に気づくために、学び合い育ち合える場をつくりました。
「人といのち」という、妙なる生態をどう感じ、どう受け入れ、どう生きていくかを、自然の中の一構成員という視点でみつめることを狙いとするため、いままで専門職を育成してきた「科学的根拠」という視点はここでは重視しません。
すべて自然の仕組みに習い(倣い)、触れ、感じ、癒されるプログラムになっています。
いのちが調和する社会の実現のために、令和元年4月に開校した「人といのちの自然学校」も7年目を迎えます。
日本の風土が育んだ自然への畏敬の念、自然と共に生きた人々が暮らしの中から生み出した文化、この豊かさの中でリレーされてきた「いのちのあり様」を感じ、丁寧に伝えあえる場が「人といのちの自然学校」です。
すべてのいのちが調和する未来にむけての一歩を、多くの人と共に踏み出していきたい。
「人といのちの自然学校」でお待ちしています。
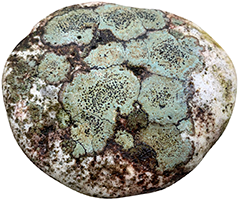
実施校
大阪校
大阪城の緑が窓に広がる明るく解放的なセミナールームです。
「いのち」をテーマに素晴らしい講師をお招きしてのセミナーを重ねてきた人といのちの自然学校開設当初からの活動拠点です。

熊野校
令和4年4月に開校した、三重県熊野市の拠点です。
高齢化が進み、空き家が増える熊野市神川町の築100年の古民家、それが循環調和、協働をテーマにした「熊野蘇和家」です。
日本の風土に育まれた文化伝統を取り戻す活動を柱に、貧困や格差の解決策の一つとしての自給、文化伝統の継承を通じた地域社会の再構築、そして、人の健康を衣食住を通して提案していきます。

